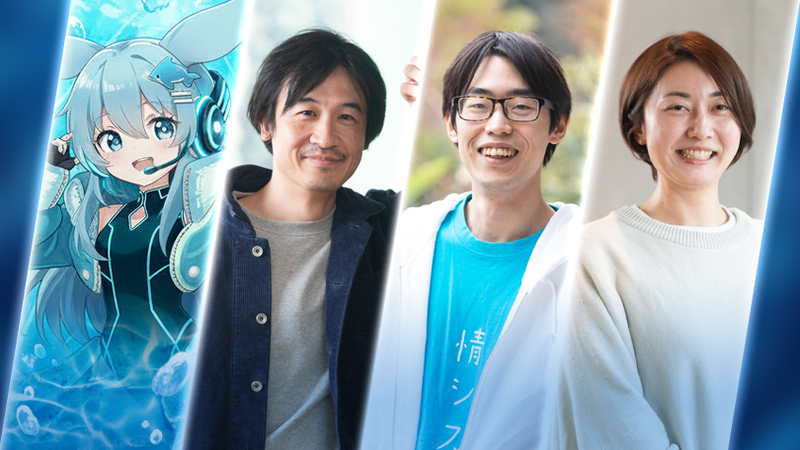今年もゲームに関する技術や知識を共有する国内最大級のカンファレンスCEDECが、2025年7月22日(火)〜24日(木)に渡り開催されました。
今回、グリーグループからは株式会社WFSが公募セッションの全8セッションに登壇。公募セッションは一般募集からの選考を経て選出されますが、例年多くの社員が応募し登壇を果たしています。登壇内容をセッションを終えた登壇者の声とともにご紹介いたします。

グリーグループからの登壇セッションと登壇者の声ご紹介
LLM翻訳ツールの開発と海外のお客様対応等への社内導入事例
講演者:郡司 匡弘、松井 望、小野 幸人
セッション内容:
多言語でグローバル配信するライブサービスゲームタイトルにおける、お客様からのお問い合わせ対応について、社内向けのLLM翻訳ツールを整備し、オペレーション工数やヒューマンエラーの削減、お客様への回答スピードの向上を図りました。何か役に立つ事があれば幸いです。
 登壇者の声:郡司 匡弘 株式会社WFS / スタジオ本部 / 技術室 / マネージャー・リードデータエンジニア
登壇者の声:郡司 匡弘 株式会社WFS / スタジオ本部 / 技術室 / マネージャー・リードデータエンジニア
ChatGPTが話題となった2年前から、World Wide Operations Group(社内の他部署、以下「WWO」)の翻訳者の方々とAIを使って翻訳業務の効率化ができないか検証してきました。ゲームシナリオのローカライズでAIを使うのは依然難しいものの、海外お問い合わせの翻訳では他社機械翻訳を上回る精度を確認でき、今回の登壇に至っています。2年間、WWOの翻訳者に、翻訳やローカライズの技術・難しさなどを教えていただき、時にはAIの翻訳品質に妥協せず指摘をしていただいたことで、AIの技術力も上がった気がします。今後もAIを使って事業サポートができるように頑張っていきます。
『ヘブンバーンズレッド』における、世界観を活かしたミニゲーム企画の作り方
講演者:菊岡 大夢
セッション内容:
『ヘブンバーンズレッド』は3年間の運営を続けるにあたり、長く楽しんでくださるプレイヤーの皆様に様々なコンテンツを提供できるよう、リズムゲーム・経営シミュレーションゲーム・ボードゲームなど様々な形態のミニゲームを提供してきました。
本セッションでは、運営タイトルにおいて日々遊び続けられるような新鮮な体験をコンスタントに提供していくための企画発想フローについて、『ヘブンバーンズレッド』のミニゲームを題材にご紹介します。
 登壇者の声:菊岡 大夢 株式会社WFS / スタジオ本部 / 第2スタジオ部 / リードゲームデザイナー
登壇者の声:菊岡 大夢 株式会社WFS / スタジオ本部 / 第2スタジオ部 / リードゲームデザイナー
「こういうゲームを作るぞ!」とゲームルールそのものを企画する機会というのは、意外に少ないように思います。社内でもそういった場面で苦戦するプランナーたちの姿を見てきたので、自身が辿った企画フローを一例として提示し、体系化して伝えることに意義がありそうと思いCEDECへの登壇を決めました。特に『ヘブンバーンズレッド』では世界観・物語体験を重視しているので、そこにフォーカスして企画手法を共有しました。開催前までは自身の講演内容にばかり意識が向いてましたが、会場では聴講者の一人として参加者と情報交換ができましたし、その内容が自身の講演にも反映できたのはスピーカーとして参加したことの醍醐味だなと感じました。
『ヘブンバーンズレッド』のレンダリングパイプライン刷新
講演者:野口 顕弘
セッション内容:
本講演では、ライブサービス型ゲーム『ヘブンバーンズレッド』のグラフィックパイプラインを、運用に支障をきたすことなく Unity の Universal Render Pipeline (URP) に移行した事例を解説します。長期的なメンテナンス性向上と将来的な機能拡張を狙い、運用チームの追加作業を極力抑え、アーティストの手間もほぼ発生させずに移行を完遂した戦略と実践手法に焦点を当てます。具体的には、URP 移行中に直面した技術的課題とその解決策、そしてライブサービス運用を維持しながらシステム刷新を実現したプロセスを共有します。
 登壇者の声:野口 顕弘 株式会社WFS / スタジオ本部 / 技術室 / シニアリードエンジニア
登壇者の声:野口 顕弘 株式会社WFS / スタジオ本部 / 技術室 / シニアリードエンジニア
ライブ運用を止めることなく『ヘブンバーンズレッド』の描画基盤を刷新するという大きな挑戦に取り組みました。Unityでは描画パイプラインが大きく更新されており、同様の課題を抱える企業も多いことから、今回CEDECで登壇しました。セッションでは、資料が乏しい旧パイプラインの挙動を整理・共有するとともに、移行プロジェクトの運用アプローチを実例とあわせて紹介。登壇後は多くのグラフィックスプログラマーと意見交換する機会にも恵まれ、情報共有にとどまらず自身の学びにもつながる、非常に貴重な経験となりました。
『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』のグローバル展開を支える、開発チームと翻訳チームの「意識しない協創」を実現するローカライズシステム
講演者:原田 大志、篠原 功
セッション内容:
近年のオンラインゲームアプリは、顧客基盤の拡大のためにも世界中のユーザに向けて展開することが求められています。
そのため、多言語対応が重視されていますが、特にストーリーやキャラクターを重視した運営型のゲームでは、UIやシステムメッセージ以外にも翻訳対象は膨大で、継続的に増えていくため、効率良くローカライズを進められるかが課題となっています。
そのためには、アプリの開発チームに負荷をかけず、翻訳チームが独立しながら作業を進めることができる環境と、それを支える翻訳対象の抽出から翻訳データのアプリへの反映まで、自動化されたシステムが必要だと考えました。
本セッションでは、スマートフォン向けゲームアプリ『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』のグローバル同時リリース、そして運営を実現するためのローカライズシステムについて、システムの全体像から言語切り替えの仕組み、開発チームと翻訳チームが密接に関わりながらも、お互いに独立して作業を進めていくための連携方法など、実際の開発中の事例も交えて紹介します。
 登壇者の声:原田 大志 株式会社WFS / スタジオ本部 / 第5スタジオ部
登壇者の声:原田 大志 株式会社WFS / スタジオ本部 / 第5スタジオ部
世界中のユーザに平等に新鮮な体験を届けるためには、複数言語、同時開発の実現が不可欠です。
しかし、技術的な問題以上に、開発チームと翻訳チームという全く異なるチーム間の連携を解決することが最も重要であると痛感しました。
この気づきにより少しでも日本のゲームが世界で躍進する手助けになればと思い、CEDECへの応募を決意しました。
そのため講演では、異なるチームを無理に協力させるのではなく、各チームが自由に作業できるような仕組みを作ることの重要性を伝えました。
登壇後も、同じような課題を抱える多くの方々と時間いっぱい意見交換ができ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。
『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』の必殺技演出を徹底解剖! -キャラクターの魅力を最大限にファンに届けるためのこだわり-
講演者:新谷 雄輝、金子 俊太朗、佐々木 文哉
セッション内容:
本講演では、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』の必殺技演出の制作手法について紹介させていただきます。
3Dを用いてキャラクターの魅力を最大限に表現した必殺技演出の制作フローと、各工程にてこだわった箇所を実例を元に紹介させていただきます。
必殺技演出の制作に興味がある方はもちろん、『魔法少女まどか☆マギカ』のファンの方にも楽しんでいただける内容となっております。
「原作再現+進化」をテーマに制作を行った、最新スマートフォン向けゲームアプリ制作の裏側や演出の考え方を全てお見せします!
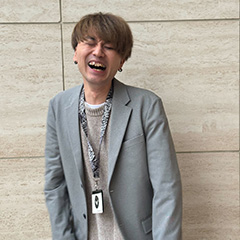 登壇者の声:新谷 雄輝 株式会社WFS / スタジオ本部 / 第4スタジオ部
登壇者の声:新谷 雄輝 株式会社WFS / スタジオ本部 / 第4スタジオ部
『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』における、必殺技演出の制作についてのこだわりを言語化、発表することで同じような悩みを持つ方たちへの情報共有が出来ればと思い、CEDECへの参加を決意いたしました。
これまで行ってきた、原作の魅力を最大限に見せるための工夫を、一つ一つ丁寧に説明することを意識して講演させていただきました。
演出づくりの資料としては初歩的な内容となっておりますが、開発初期から一貫して掲げていたテーマや、言語化の大切さをお伝え出来たかと思います。また、会場では同じ志を持つ開発者の方たちとお話もでき、とても良い刺激をいただきました。この経験を糧に、より良い演出づくりを行ってまいります。
ライブサービスゲームQAのパフォーマンス検証による品質改善の取り組み
講演者:小野 粋哉、勅使川原 大輔
セッション内容:
本セッションではライブサービスゲームのパフォーマンス検証の取り組みについて説明します。
昨今のライブサービスゲーム開発では、グラフィックや演出の高度化が進み、リッチな体験が求められる一方で、限られた端末リソースを考慮したパフォーマンス最適化が不可欠です。
また、正確なパフォーマンスを計測するには、ツール導入などコスト面のハードルもありますが、今回はツールを用いずかつ体系的なパフォーマンス検証の仕組みづくりについて具体例を交えながら解説します。
検証フローの構築や端末選定など実践的な知見を共有します。
 登壇者の声:小野 粋哉 株式会社WFS / Customer & Product Satisfaction部 / QAグループ
登壇者の声:小野 粋哉 株式会社WFS / Customer & Product Satisfaction部 / QAグループ
ライブサービスゲームを運営するにあたって、ゲーム内の表現、演出がリッチ化している中でパフォーマンス面における課題も重要になっていると感じていました。
なかには、特定の状況や端末で発生することもあり、それが影響してゲーム内の評価が落ちたり、運営の信頼が低下することもあります。それらをどういうアプローチで防いでいるかを共有したいと考え登壇いたしました。
会場では同じ課題を持つ開発者の方ともお話しすることができ、大変有意義な時間を過ごすことができました。
ヒューリスティック評価を用いたゲームQA実践事例
講演者:山本 幸寛
セッション内容:
ライブサービスゲームのテストを行うにあたり今までのリリース前のテストだけでは、検知された不具合の修正コスト、手戻りの困難さの課題をかかえております。そこで、仕様書やごく初期のプロトタイプでも評価が行える、かつ、低コストで導入が可能な「ヒューリスティック評価」をライブサービスゲームに導入し、初期品質向上の取り組みをご紹介したいと思います。
本セッションではユーザビリティ研究の第一人者でもある「ヤコブ・ニールセン博士」によって提唱された評価手法をベースに、ライブサービスゲーム向け観点として「継続意向」「課金意向」「ユーザー満足度」の視点で分析できるようにカスタマイズした評価項目を用いて、実際に適用した事例と導入結果から見えてきた課題および今後の展望についてお伝えいたします。
 登壇者の声:山本 幸寛 株式会社WFS / Customer & Product Satisfaction部 / QAグループ
登壇者の声:山本 幸寛 株式会社WFS / Customer & Product Satisfaction部 / QAグループ
ゲームQAとして「当たり前品質」を守ることはもちろん、プレイヤーをより惹きつける「魅力的品質」の向上に貢献したいという思いから、新たな手法の導入に挑戦しました。それが、ソフトウェアテストで主に用いられる「ヒューリスティック評価」となります。この手法が低コストでUI/UX課題を早期に発見するのに有効であると実感し、その知見を皆様にも共有したいと考え登壇いたしました。
当日は、UI課題の早期発見や新たなQAアプローチに関心を持つ多くの方々と直接意見交換ができ、大変有意義な時間となりました。
『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』での負荷試験の実践と学び
講演者:悦田 潤哉
セッション内容:
大規模なソーシャルゲームをリリースする前には、安定したゲームプレイを提供するために負荷試験が必要不可欠となります。
このセッションでは、GKE、Spanner、Memorystore for Memcached、PHP というサーバー構成で、jmeterを用いて40,000 RPS の負荷試験を達成した実例を紹介します。
負荷試験の目的や設定した目標値、技術的な工夫や直面した課題とその解決策、更にjmeterを使った負荷の生成方法と特有の課題についてもお話し致します。
また、本作は 国内・海外同時リリースをしており、海外からのアクセスを考慮したサーバー構成の紹介と負荷試験においてどのように海外からのアクセスを再現したかについても触れます。
これから負荷試験を考えているプロジェクトおよびエンジニアの皆さんにとって有益な情報となれば幸いです。
 登壇者の声:悦田 潤哉 株式会社WFS / スタジオ本部 / 第4スタジオ部
登壇者の声:悦田 潤哉 株式会社WFS / スタジオ本部 / 第4スタジオ部
大規模タイトルのリリースでは、想定外のトラブルが致命的な障害につながるリスクがあります。『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』の負荷試験から得た「負荷試験は単なる性能測定ではなく運用リハーサル」という学びを共有したく応募しました。
セッションでは実際に遭遇した問題と解決策を具体的に示し、同じ悩みを抱える皆様に知見を共有できたかと思います。AskTheSpeakerではセッションの中で話せなかった内容の深掘りや他社事例との比較、アーキテクチャの情報交換など、大変有意義な時間を過ごせました。
負荷試験はサービスリリースに不可欠なので、今後のプロジェクトでこの経験を活かしていきたいです。